全固体電池の実用化が迫る!主要メーカーと普通の電池との違いを徹底解説
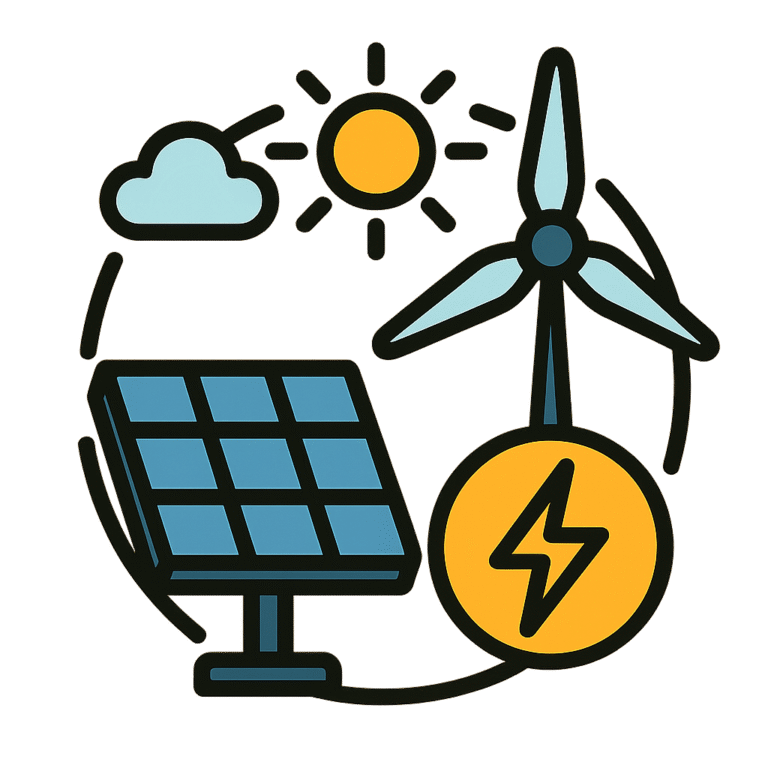 Chemistry
Chemistry
電気自動車の普及とともに注目を集める全固体電池。2027年の実用化を目前に控え、関連銘柄への投資熱も高まっている。従来のリチウムイオン電池を凌駕する性能を持つこの次世代技術について、その原理から実用化の展望、主要メーカーの動向まで詳しく解説する。
全固体電池とは?普通の電池との決定的な違い
全固体電池の最大の特徴は、電解質が液体ではなく固体である点だ。従来のリチウムイオン電池では、正極と負極の間を液体電解質がイオンの通り道として機能している。これに対し、全固体電池ではセラミックや硫化物などの固体材料がその役割を果たす。
全固体電池の原理
この違いがもたらすメリットは計り知れない。まず安全性が飛躍的に向上する。液体電解質は可燃性で液漏れや発火のリスクがあるが、固体電解質は不燃性で、これらの危険性が大幅に低減される。実際、熱暴走時の持続時間は従来の500ミリ秒から5ミリ秒へと100分の1に短縮される。
性能面でも圧倒的な優位性を持つ。エネルギー密度は従来の250-300Wh/kgから400-500Wh/kgへと約2倍に向上し、同じ大きさでより多くの電気を蓄えられる。充電時間も従来の20-30分から9-15分へと半減し、将来的には10分以下での急速充電も可能になる。
 これまでの電池は液漏れのリスクがあり,容量も小さい。
これまでの電池は液漏れのリスクがあり,容量も小さい。
実用化はいつ?主要メーカーの最新動向
全固体電池の実用化は、もはや「いつか」の話ではない。2025年から2030年にかけて、主要メーカーが続々と商用化を開始する予定だ。
トヨタが世界をリード
トヨタは全固体電池開発の最前線を走る。2006年から研究開発を開始し、8000件以上の関連特許を保有する世界トップ企業だ。同社は2027-2028年に全固体電池搭載EVの市場投入を明言している。
トヨタの強みは、出光興産との協業体制にある。出光は硫化物系固体電解質の製造技術に優れており、両社で年間1,000トンの生産体制を構築する。トヨタは135億ドルを投資し、2030年までに年間9GWhの生産能力を目指している。

出光とトヨタ、バッテリーEV用全固体電池の量産実現に向けた協業を開始 | コーポレート | グローバルニュースルーム | トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト
出光興産株式会社(以下、出光)とトヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ)は、バッテリーEV(以下、BEV)用の有力な次世代電池である全固体電池の量産化に向けて、固体電解質の量産技術開発や生産性向上、サプライチェーン構築に両社で取り組むことを、本日意思決定し、合意しました。全固体電池の材料開発等で世界をリードする両社が連携す...
その他の注目メーカー
サムスンSDIは2027年に量産開始予定で、エネルギー密度900Wh/Lという驚異的な性能を実現する。日産は2025年3月からパイロット生産を開始し、2028-29年度に商用EV生産を計画。従来比2倍のエネルギー密度と75ドル/kWhというコスト目標を設定している。
中国勢ではCATLとBYDが国家支援のもと開発を加速。欧米ではBMWとフォードがソリッドパワー社に1.3億ドルを共同投資するなど、世界中で開発競争が激化している。
注目の関連銘柄
全固体電池関連銘柄として注目すべき企業は多い。自動車メーカーでは、トヨタ(7203)、日産(7201)、ホンダ(7267)が挙げられる。電池・素材メーカーでは、村田製作所(6981)、TDK(6762)、出光興産(5019)、三井金属(5706)などが有望だ。
海外銘柄では、韓国のサムスンSDI、LGエネルギーソリューション、米国のクァンタムスケープ、ソリッドパワーなどが注目される。これらの企業は、全固体電池の実用化により大きな成長が期待できる。

幅広い用途展開
全固体電池の用途は電気自動車だけではない。スマートフォンやウェアラブルデバイスでは、薄型化・小型化のメリットを活かし、より長時間駆動する製品の実現が可能になる。
医療機器分野では、ペースメーカーや植込み型除細動器で生体適合性と長寿命を提供する。液漏れの心配がないため、体内での使用も安全だ。航空宇宙分野では、-40°C~150°Cという極限環境でも安定動作する特性が評価されている。
さらに、再生可能エネルギーの蓄電システムとしても期待が高い。太陽光や風力発電の不安定な出力を安定化させる大規模蓄電池として、全固体電池は理想的な選択肢となる。
革新的な素材と原理
全固体電池の性能を左右するのが固体電解質の素材だ。主に3種類の材料が開発されている。
酸化物系(セラミック系)は耐久性が高く長寿命だが、イオン伝導度がやや低い。硫化物系は1-25mS/cmという高いイオン伝導度を誇るが、湿気に弱く取り扱いに注意が必要だ。ポリマー系は柔軟性があり加工しやすいが、室温での性能向上が課題となっている。
原理的には、リチウムイオンが固体電解質の結晶格子中を「ホッピング」することで電気を生み出す。この移動メカニズムにより、液体電解質では不可能だった高温・低温環境での安定動作が可能になる。
全固体電池のデメリットと課題
メリットばかりが注目される全固体電池だが、デメリットや課題も存在する。最大の課題は製造コストだ。現在の製造コストは175ドル/kWhと高額で、商用化には100ドル/kWhまでの低減が必要とされる。
また、固体-固体界面の接触抵抗も技術的な課題だ。液体と異なり、固体同士の接触では微細な隙間が生じやすく、これがイオンの移動を妨げる。さらに、大量生産技術の確立も急務となっている。
しかし、これらのデメリットは技術革新により着実に解決されつつある。AIを活用した材料設計や、新たな製造プロセスの開発により、2030年までには多くの課題が克服される見込みだ。
まとめ:全固体電池が変える未来
全固体電池は、単なる電池の進化ではない。エネルギー貯蔵の概念そのものを変革する技術だ。2027年のトヨタによる実用化を皮切りに、2030年代には私たちの生活に欠かせない存在となるだろう。
関連銘柄への投資を検討する際は、各メーカーの技術力、特許数、提携関係などを総合的に判断することが重要だ。全固体電池は、次世代のエネルギー社会を支える基幹技術として、今後も注目し続ける価値がある。
参考
https://article.murata.com/ja-jp/article/basic-lithium-ion-battery-4
https://evdays.tepco.co.jp/entry/2024/01/15/000053
https://www.sbbit.jp/article/cont1/37046
https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20220720.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241126/k10014649361000.html

図解入門よくわかる最新全固体電池の基本と仕組み[第2版] | 齋藤勝裕 | 工学 | Kindleストア | Amazon
Amazonで齋藤勝裕の図解入門よくわかる最新全固体電池の基本と仕組み。アマゾンならポイント還元本が多数。一度購入いただいた電子書籍は、KindleおよびFire端末、スマートフォンやタブレットなど、様々な端末でもお楽しみいただけます。
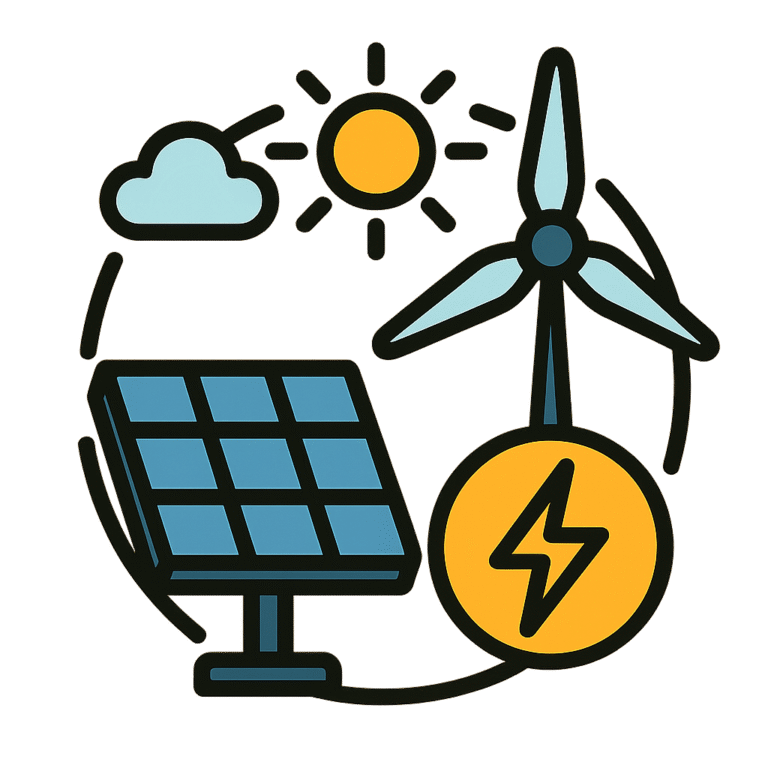




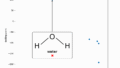
コメント