はじめに
20世紀において「奇跡の鉱物」と呼ばれたアスベスト。その優れた物理的特性により産業発展に大きく貢献した一方で、深刻な健康被害の発覚により現在では世界的に使用が禁止されている。最近,旭化成建材で過去に販売されていた材料にアスベストが含まれていたと発表されたのは記憶に新しい。
https://www.asahikasei-kenzai.com/news/pdf/20250711_release.pdf旭化成建材で本材料が販売されていたのは1996までなので今後誤って購入することはないが,解体の時に問題となる可能性はある。本記事では、アスベストの有用性から危険性、規制の変遷、そして現在の状況まで、この複雑な問題の全貌を解説する。
アスベストの驚異的な特性
アスベストは天然に産出する繊維状ケイ酸塩鉱物である。その最大の特徴は、単一材料で複数の優れた特性を併せ持つことである。繊維直径は0.02-0.35μmと髪の毛の約1/5,000という超微細さでありながら、鋼鉄を上回る引張強度を有する。
最も重要な特性は,1,000℃以上の耐熱性と完全な不燃性である。さらに、ほとんどの化学物質に対する不活性、水や有機溶媒に不溶という化学的安定性も備えている。これらの特性により、建築・工業分野での広範囲な使用が可能となったのである。
アスベストは鉱物学的に6種類に分類される。クリソタイル(白石綿)は全使用量の約95%を占め、カールした繊維構造により織物加工に適していた。一方、アモサイト(茶石綿)とクロシドライト(青石綿)は角閃石系で、直線的で針状の繊維構造を持ち、より高い危険性を示す。
建築分野では全用途の約80%が使用され、1955年から1989年にかけて吹付け材として、またスレート材、断熱材、セメント製品として広く利用された。工業分野では配管・ボイラーの断熱材、電気絶縁材として、船舶業界では機関室の耐火材や船体断熱材として不可欠な材料であった。
深刻な健康被害の実態
アスベストによる健康被害は極めて深刻で多様である。最も重篤なのは中皮腫で、WHOの推定では症例の90%以上がアスベスト暴露によるものとされる。胸膜中皮腫が最も一般的(約75-80%)で、診断後の平均生存期間は8-14か月と極めて予後不良である。
肺がんは特に喫煙者において顕著にリスクが増加し、喫煙とアスベスト暴露の組み合わせは個別リスクの単純な和を超える相乗効果を示す。石綿肺は長期間の高濃度暴露により発症する肺線維症で、肺組織の瘢痕化により呼吸困難を引き起こす。
吸入された微細な繊維は肺の最末端部(肺胞)に沈着し、生体内でほぼ永続的に残存する。マクロファージによる貪食過程で慢性炎症と酸化ストレスが持続的に発生し、細胞のDNA損傷を引き起こす。
アスベスト関連疾患の最も特徴的な点は極めて長い潜伏期間である。中皮腫は平均33.7年(範囲:11-72年)、肺がんは平均40.1年の潜伏期間を示す。この長期潜伏期間により、暴露終了後数十年経過してから発症するため、因果関係の特定が困難になっている。
用量反応関係が確認されており、累積暴露量と発症リスクは正の相関を示すが、安全閾値は存在しないとWHOは結論付けている。重度暴露者では8-13%が中皮腫を発症し、短期間の集中的高濃度暴露でも発症例が報告されている。

規制の世界的な広がり
現在、67か国がアスベストを全面禁止しており、禁止は世界的な潮流となっている。1983年のアイスランドが世界初で、1980年代から1990年代にかけて北欧諸国が相次いで禁止し、2005年にはEU全域で禁止された。
アメリカでは2024年3月にEPAがクリソタイル石綿の製造・輸入・使用を禁止するTSCA規則を最終化したが、2025年2月に第5巡回控訴裁判所が訴訟を120日間停止し、現在EPAが政策見直しを実施中である。特定用途(防衛産業、原子力施設)では例外措置が維持されている。
EUでは2023年11月に作業者保護規則を強化し、職業暴露限度値を0.1繊維/cm³から0.01繊維/cm³に引き下げ、2029年12月までに更に0.002繊維/cm³に削減予定である。
日本では1975年に吹付け石綿の原則禁止から始まり、段階的に規制を強化してきた。1995年に青石綿・茶石綿の製造・使用等を禁止、2004年に10品目の禁止、2006年に重量の0.1%を超える製品の全面禁止を経て、2012年3月1日に完全禁止を達成した。
歴史的な経緯と社会問題化
アスベストの使用歴史は約4,500年前まで遡る。古代フィンランドでは陶器の強化材として、古代エジプトではミイラを包む布として、古代ギリシャでは「汚れない」という意味の「アミアントス」と呼ばれランプの芯として使用されていた。
日本では平賀源内が1764年に秩父山中で発見し、火浣布を製作して江戸幕府に献上したのが最初の記録である。商業的採掘は1858年にアメリカで始まり、1879年にカナダで初の工業的鉱山が開設された。
19世紀後半から20世紀前半にかけて、産業革命により断熱材、防火材として需要が急増した。カナダは20世紀を通じて世界最大の生産国で、1973年にピーク169万トンを記録した。日本では戦後復興期から高度経済成長期にかけて大量使用され、累積輸入量は約1,000万トンに達した。
健康被害については、1900年に英国で初の健康被害報告があったが、本格的な科学的証拠は1930年から始まった。1955年に肺がんとの関連、1960年に中皮腫との関連が確認され、1970年代にWHO、IARCが発がん性を確認した。
産業界による隠蔽問題は深刻で、1930年代から危険性を認識しつつ隠蔽を続けていた。1970年代にアメリカ裁判所が産業界の隠蔽を認定し、1982年にジョンズ・マンビル社が高額賠償により事実上倒産した。
日本では2005年のクボタ・ショックが転換点となった。尼崎工場で従業員78人が中皮腫で死亡、周辺住民434人が発症という深刻な環境汚染被害が発覚し、これを契機に石綿健康被害救済法が制定された。
現在の状況と今後の課題
世界では年間約20万人がアスベスト関連疾患で死亡しており、2019年には239,330人の死亡が報告されている。日本では中皮腫死亡者数が1995年の500人から2019年の1,466人に増加し、2025年頃まで増加が続くと予測されている。
近年、免疫療法の導入により中皮腫の生存期間が18.1か月に延長された。ニボルマブ+イピリムマブの併用療法は化学療法に優越し、3年生存率は23%を達成している。診断技術ではCTガイド下生検、血清メソテリン、AI画像診断による早期発見技術が進歩している。
代替材料の開発が進み、現在はファイバーグラス、セラミック繊維、ロックウール等が用途に応じて使用されている。しかし、アスベストの全ての特性を単一材料で代替することは困難であり、複数材料の組み合わせによる対応が一般的である。
既存建物の対策が重要な課題となっており、2006年以前建築物の大部分に石綿含有建材が使用されているため、今後の大規模改修・解体需要の増加に対応した体制整備が必要である。
67カ国での禁止にも関わらず、中国、ロシア、インド、ブラジル等では依然として使用が継続されている。WHO、ILOは全形態のアスベスト使用停止を強く推奨し、国際的な取り組みが続けられている。
おわりに
アスベストは20世紀において産業発展に大きく貢献した「奇跡の鉱物」であったが、その後の深刻な健康被害により世界的に禁止された物質となった。単一材料で複数の優れた特性を併せ持つ稀有な素材であったため広範囲に使用されたが、極めて長い潜伏期間と治療困難な疾患を引き起こす危険性が判明した。
現在では多くの国が禁止し、診断・治療技術の進歩により予後は改善傾向にあるものの、既存建物からの暴露対策と長期的な健康監視が重要な課題として残っている。アスベスト問題は、産業発展と公衆衛生の調和、企業の社会的責任、政府の規制責任を問う重要な歴史的教訓として、今後の化学物質管理に活かされるべき事例である。
参考
https://news.yahoo.co.jp/articles/a092293398d660bf8cc9b78e2e0c799a504956e7
https://build-up.jp/work/2289/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/topics/tp050729-1.html
https://www.erca.go.jp/asbestos/what/higai/mechanism.html

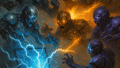
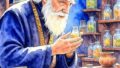
コメント